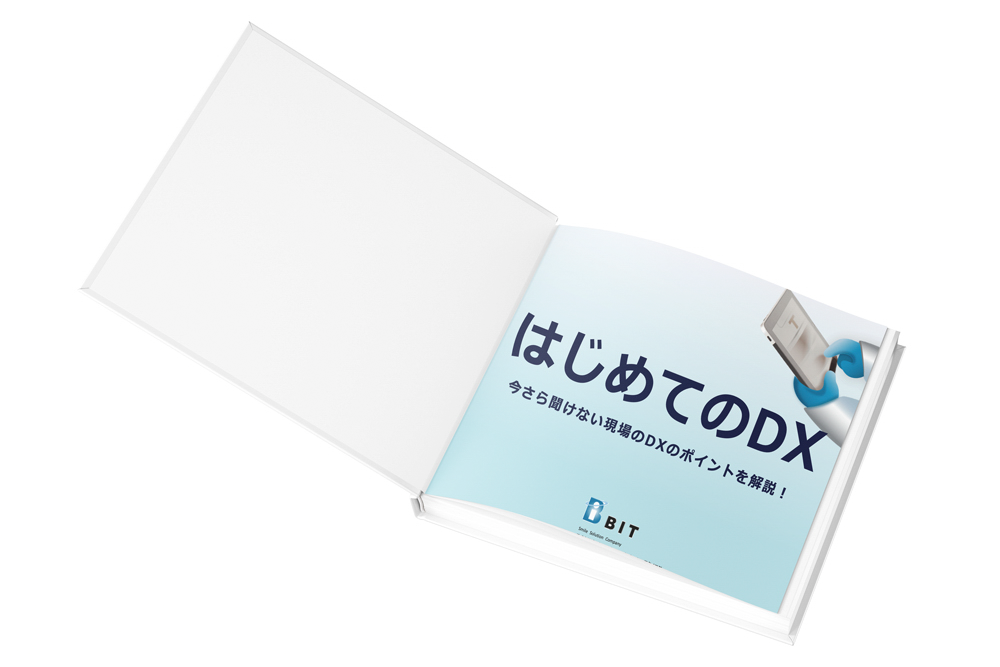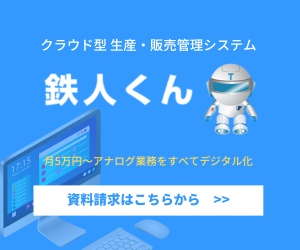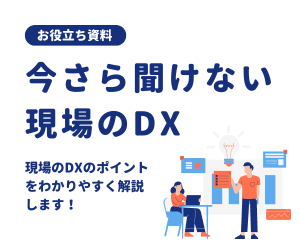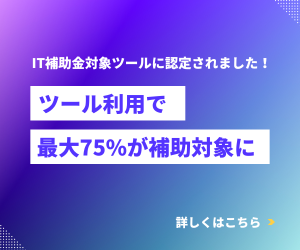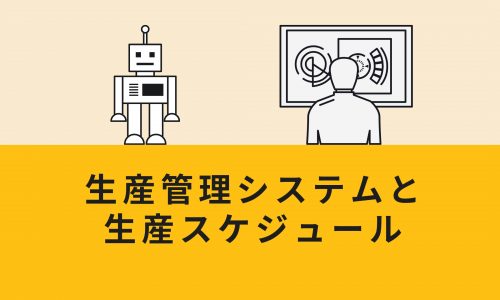新しいシステム導入は、業務効率化や競争力向上に不可欠な一方、多大なコストと労力を要するプロジェクトです。もし導入したシステムが自社の業務に合わなければ、その投資は大きな損失になりかねません。このような失敗を未然に防ぎ、システム導入を成功に導くための強力な手法が「フィットギャップ分析」です。
本記事では、フィットギャップ(Fit&Gap)分析の基本的な知識から、具体的な進め方、失敗しないための注意点までを網羅的に解説します。
合わせて読みたい
「製造業のムダをなくす!「わかりやすい業務フロー」作成の極意」
3分でわかる!はじめてのDX
今さら聞けない現場のDXのポイントを解説!
お役立ち資料はこちらから無料ダウンロードいただけます。
フィットギャップ分析とは?システム導入を成功に導く基本
まずは、フィットギャップ分析がどのようなもので、なぜ重要なのかを理解しましょう。
フィットギャップ分析の定義と目的
フィットギャップ分析とは、新しく導入を検討しているパッケージシステムやサービスが持つ機能と、自社の業務要件や求める機能が、どれだけ適合しているか(Fit)、そしてどれだけ乖離しているか(Gap)を明らかにする分析手法です。
その主な目的は、システム導入の価値を客観的に測り、導入プロジェクトの失敗リスクを最小限に抑えることにあります。
なぜシステム導入にフィットギャップ分析が不可欠なのか?
勘や期待だけでシステムを選定してしまうと、
「導入したものの、使いたい機能がなかった」
「現場の業務フローと合わず、かえって非効率になった」
といった問題が発生しがちです。
フィットギャップ分析を通じて、事前に業務要件とシステム機能のズレを正確に特定することで、自社のニーズに最も適したシステムを選び、円滑な導入と運用を実現できます。これは、自社の将来のビジョンや経営戦略に沿ったシステム投資を行う上でも不可欠なプロセスです。
フィットギャップ分析の具体的な進め方【5ステップ】
フィットギャップ分析は、以下の5つのステップで進めるのが一般的です。
Step1: 準備(目的の明確化と適切な体制の構築)
まず、なぜシステムを導入するのか、その目的を明確にします。
次に、情報システム部門だけでなく、実際にシステムを利用する業務部門の担当者など、関係各所からメンバーを集め、分析のための体制を構築します。
Step2: 現状把握(業務プロセスの可視化と要件の洗い出し)
現在の業務フローを詳細に洗い出し、図や文書で「可視化」します。
その上で、新しいシステムに求める機能要件(〇〇ができること)と非機能要件(パフォーマンスやセキュリティなど)をリストアップします。
Step3: 分析の実施(Fit部分とGap部分の特定)
Step2で作成した要件リストと、導入候補システムの機能一覧を一つひとつ照らし合わせます。
- Fit(適合): 要件をシステムの標準機能で満たせる項目。
- Gap(乖離): 要件をシステムの標準機能で満たせない項目。
この2つに分類し、すべての要件を整理していきます。
Step4: ギャップへの対応方針の決定
特定された「Gap」に対して、どのように対応するかを検討します。Fit率の低さを放置して導入を強行すると、失敗のリスクが高まるため、このステップは極めて重要です。具体的な対応策は後述します。
Step5: 分析結果のとりまとめと評価
分析結果を報告書としてまとめます。Fit/Gapの一覧、Gapへの対応方針、それにかかる追加コストや期間の見積もりなどを記載し、最終的な導入可否や最適な製品を判断するための材料とします。
【実践】ギャップへの3つの具体的な対応策
分析で見つかった「Gap」への対応は、大きく分けて3つの選択肢があります。
1. システムを自社の業務に合わせる(追加開発・カスタマイズ)
システムの機能を追加・改修(カスタマイズ)して、自社の業務フローに合わせる方法です。既存の業務を変えずに済みますが、追加の開発コストや時間がかかり、将来のバージョンアップが困難になるリスクもあります。
2. 業務をシステムに合わせる(業務プロセスの変更)
システムの標準機能に合わせて、自社の業務プロセスの方を変更する方法です。これは「Fit to Standard」とも呼ばれ、カスタマイズ費用を抑え、短期間での導入が可能になるメリットがあります。
3. 代替案や運用でカバーする
Gapが業務の根幹に関わらない軽微なものである場合、Excelでの手作業や別のツールを併用するなど、システム外の運用でカバーする方法です。
フィットギャップ分析で陥りがちな失敗と成功のポイント
分析を成功させるためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
よくある失敗事例とその原因
- 要件の洗い出し不足: 現場の細かい業務や例外処理が漏れており、導入後にGapが発覚する。
- 関係者の協力不足: 業務部門の協力が得られず、現状の業務を正しく把握できない。
- Gapの安易な放置: 見つかったGapへの対応を曖昧にしたまま導入を進め、現場が混乱する。
分析の精度を高める関係者との連携術
成功の鍵は、関係者をいかに巻き込むかにかかっています。
プロジェクトの初期段階から目的とゴールを共有し、特に現場のキーパーソンに積極的に参加してもらうことで、現実的で精度の高い要件定義が可能になります。
すぐに使える!フィットギャップ分析のテンプレート項目例
分析結果は、以下のような一覧表で管理すると分かりやすくなります。
フィットギャップ分析の結果を最大化する活用術
分析は、実施して終わりではありません。その結果をどう活かすかが重要です。
分析結果に基づく最適なシステム選定と導入計画
複数の候補製品を同じ基準で比較評価できるため、客観的で納得感のある製品選定が可能になります。
また、Gapへの対応にかかる工数やコストが明確になるため、より現実的な導入計画を立てることができます。
導入後の効果測定と継続的な業務改善
導入後、「分析時にGapだった業務は改善されたか」「Fitだと判断した機能は想定通り活用されているか」などを評価することで、投資対効果を測定し、さらなる業務改善のサイクルにつなげることができます。
まとめ:フィットギャップ分析で自社に最適なシステム導入を実現しよう
フィットギャップ分析は、システム導入という大きな投資を成功させるための羅針盤です。
この分析を通じて、自社の業務とシステムとの適合度を正確に把握し、課題への対応策を事前に検討することで、導入後の「こんなはずではなかった」という事態を防ぐことができます。
本記事で紹介したステップやポイントを参考に、ぜひフィットギャップ分析に取り組み、自社に最適なシステム導入を実現してください。
クラウド型生産管理システム「鉄人くん」は、わかりやすい画面と手厚いサポートで、システムが初めても企業でも使いやすくわかりやすいのが特徴です。
また、トライアルキャンペーンも実施していますので、生産管理システムの導入を検討してみたいとお考えの方は、こちらからお気軽にお問合せ・ご相談ください。