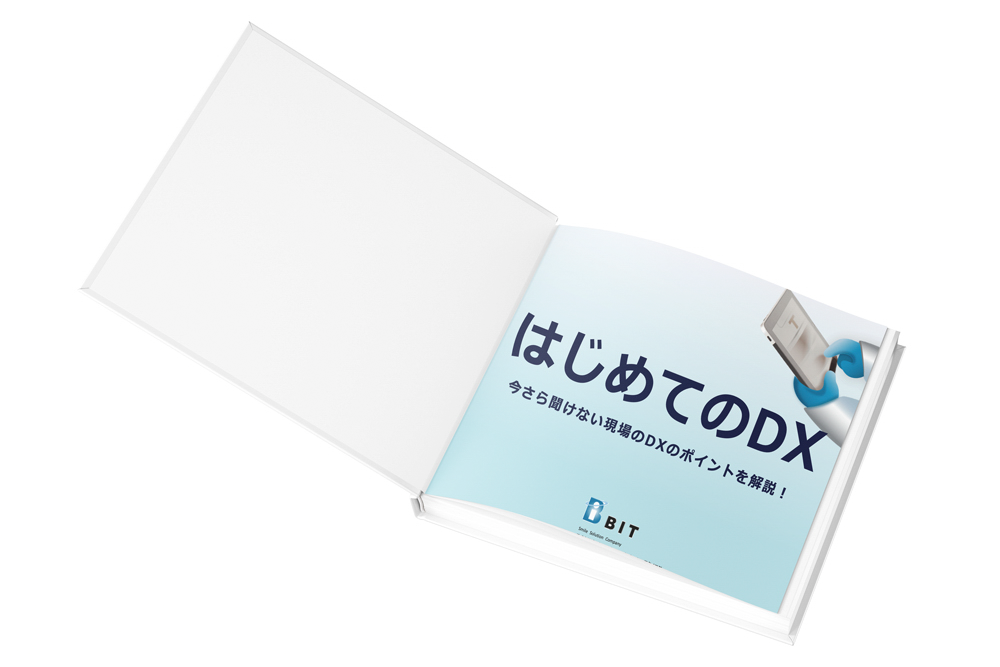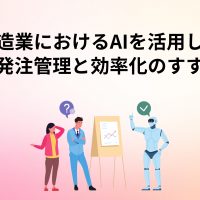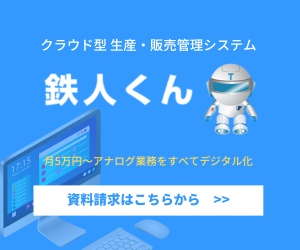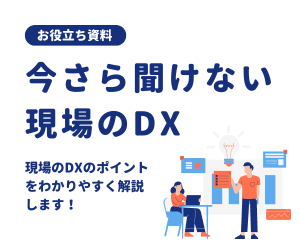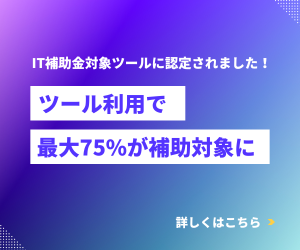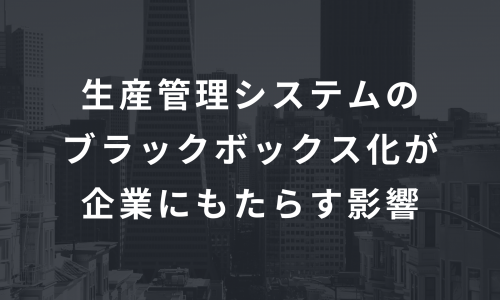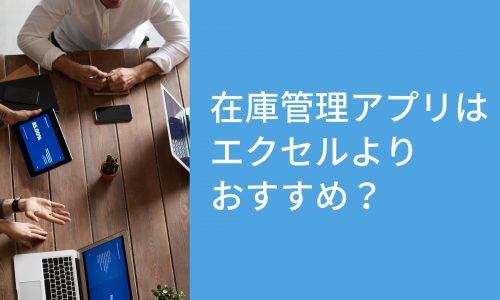「電話が鳴り止まない」「FAXの文字が読み取れない」「受注内容の入力作業が終わらない…」。もし、あなたの会社がこのような状況にあるなら、それは事業が成長している証拠であると同時に、業務プロセスが限界に達しているサインかもしれません。
電話・FAX・メールといった従来のアナログな受発注業務は、ヒューマンエラーを誘発し、多くの時間を奪い、従業員の疲弊と顧客満足度の低下を招きます。この悪循環を断ち切り、企業を次の成長ステージへと導く鍵が「受発注システム」の導入です。
この記事では、受発注システムの導入を検討している企業の担当者様に向けて、その具体的なメリットから、事前に知っておくべきデメリット、そして自社に最適なシステムを選ぶためのポイントまでを網羅的に解説します。
合わせて読みたい
「製造業で受発注システムが導入される理由は競争力強化と業務効率化|デメリット対策は?」
3分でわかる!はじめてのDX
今さら聞けない現場のDXのポイントを解説!
お役立ち資料はこちらから無料ダウンロードいただけます。
FAX・電話での受発注業務、こんな課題ありませんか?
システム導入の検討を始める前に、まずは現状の課題を明確にしましょう。多くの中小企業が、以下のような共通の悩みを抱えています。
課題1:手入力や転記作業に追われ、残業が常態化している
受け取ったFAXやメールの内容を、販売管理ソフトやExcelに一件ずつ手作業で入力する。この単純ながらも時間のかかる作業が、担当者のリソースを大きく圧迫しています。特に月末や繁忙期には注文が集中し、入力作業のためだけに残業せざるを得ない、というケースも少なくありません。
課題2:注文の聞き間違いや入力ミスで、クレームや返品が発生している
電話での注文は「聞き間違い」、手書きFAXは「読み間違い」、そしてシステムへの「入力間違い」。アナログな業務には、人為的ミス(ヒューマンエラー)が入り込む隙が数多く存在します。たった一つのミスが、誤った商品の発送に繋がり、結果として顧客からのクレーム、返品・再発送のコスト、そして信用の失墜といった大きな損失を招いてしまいます。
課題3:「在庫ある?」の電話対応だけで1日が終わってしまう
取引先からの在庫や納期に関する問い合わせ電話は、本来の業務を頻繁に中断させます。担当者はその都度、在庫管理表を確認したり、倉庫に確認しに行ったりと、多くの時間を対応に費やすことになります。この確認作業がボトルネックとなり、お客様を待たせ、ビジネスのスピードを鈍化させる原因となっています。
受発注システムとは?アナログ業務をデジタル化する仕組み
受発注システムとは、これまで電話・FAX・メールなどで行っていた企業間の商品の注文(発注)と、注文を受ける作業(受注)を、インターネットを通じてデジタル化・自動化する仕組みのことです。発注側(買い手)は専用のWebサイトから24時間いつでも商品を注文でき、受注側(売り手)はその注文データをシステム上で一元的に管理できます。これにより、アナログ業務が抱える多くの課題を根本から解決します。
受発注システム導入で得られる6つの主要メリット
受発注システムを導入することで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。ここでは代表的な6つのメリットをご紹介します。
メリット1:受注業務の自動化で、作業時間が大幅に削減される
最大のメリットは、業務の圧倒的な効率化です。取引先がシステム経由で直接注文を入力するため、電話応対やFAXの確認、システムへの手入力といった作業が一切不要になります。ある調査では、システム導入によって受発注業務にかかる時間を80%以上削減できたという事例もあります。これにより、担当者はもっと付加価値の高いコア業務に集中できるようになります。
メリット2:人為的ミスが激減し、クレーム対応コストがなくなる
発注データが直接システムに登録されるため、転記ミスや入力ミスといったヒューマンエラーの発生を根本から防ぎます。これにより、誤出荷やそれに伴うクレーム対応、返品処理といった無駄なコストと労力を削減できます。正確でスピーディーな対応は、企業の信頼性向上に直結します。
メリット3:24時間365日注文を受け付け、販売機会の損失を防ぐ
システムは24時間365日、休むことなく注文を受け付けます。これは、取引先の都合の良いタイミングでいつでも発注できることを意味し、企業の営業時間外に発生していたであろう販売機会の損失を防ぎます。特に、営業担当者が不在の時や休日に注文したいというニーズに応えられる点は大きな強みです。
メリット4:リアルタイムな在庫情報共有で、問い合わせ対応が不要になる
在庫管理システムと連携させることで、取引先はWebサイト上でリアルタイムに在庫数を確認できるようになります。これにより、「在庫はありますか?」といった定型的な問い合わせ電話が激減し、担当者の負担を大幅に軽減します。顧客自身で必要な情報を確認できるため、待ち時間のないスムーズな発注体験を提供できます。
メリット5:顧客満足度が向上し、リピート率アップに繋がる
「いつでも注文できる」「ミスがなく安心できる」「納期回答が速い」。これら全てが顧客満足度の向上に繋がります。スムーズで快適な発注プロセスは、取引先にとっての利便性を高め、「またこの会社から買いたい」というリピート注文を促進する重要な要素となります。
メリット6:蓄積されたデータを分析し、経営戦略に活かせる
システムには、「どの取引先が」「いつ」「どの商品を」「どれくらい」注文したか、といった貴重なデータが蓄積されていきます。これらのデータを分析することで、売れ筋商品の特定、顧客ごとの発注パターンの把握、需要予測などが可能になり、よりデータに基づいた客観的で戦略的な意思決定に役立てることができます。
導入前に知っておきたいデメリットと、その対策
多くのメリットがある一方で、導入前にはデメリットもしっかりと把握し、対策を検討しておくことが重要です。
デメリット1:導入・運用にコストがかかる
システムの導入には、初期費用や月々の利用料(ランニングコスト)が発生します。これを単なる「出費」と捉えるのではなく、業務効率化によって削減できる人件費や、ミスの削減による損失防止効果などを算出し、「投資」として費用対効果(ROI)を検討することが重要です。
デメリット2:取引先や社内への説明・教育が必要になる
新しいシステムを導入するには、発注をお願いする取引先への説明と協力依頼が不可欠です。また、社内の担当者も新しい業務フローに慣れる必要があります。スムーズに移行するためには、導入のメリットを丁寧に説明し、分かりやすいマニュアルを用意したり、社内勉強会を実施したりといった丁寧なフォローが成功の鍵となります。
【BtoB取引向け】受発注システムの種類と特徴
BtoB向けの受発注システムは、主に2つのタイプに分けられます。自社のビジネスモデルに合うのはどちらかを確認しましょう。
種類1:ECサイトのように利用できる「カート型」
発注側がWebサイトの商品一覧から、ECサイトで買い物をするように商品をカートに入れて発注するタイプです。直感的な操作性が魅力で、多くの企業で採用されています。取引先ごとに表示する商品や価格(掛け率)を変更できるなど、BtoB特有の商習慣に対応した機能が充実しています。
種類2:取引先ごとに専用画面を用意する「EDI型」
EDI(電子データ交換)は、専用回線やインターネットを通じて、企業間で注文書や請求書などのデータを統一された形式でやり取りする仕組みです。特に大手の小売業と多数のサプライヤー間などで利用されてきました。信頼性は高いですが、導入コストが高く、特定の取引先との専用システムになることが多いです。
失敗しない!自社に合った受発注システムの選び方 4つのポイント
数あるシステムの中から、自社に最適なものを選ぶための4つのチェックポイントをご紹介します。
ポイント1:提供形態(クラウド型 vs オンプレミス型)
現在主流なのは、サーバーを持たずにインターネット経由で利用する「クラウド型(SaaS)」です。初期費用を抑えられ、メンテナンスも不要なため、特に中小企業にはクラウド型がおすすめです。対して、自社サーバーにシステムを構築する「オンプレミス型」は、カスタマイズ性が高いですが、高額な初期投資と専門知識が必要です。
ポイント2:自社の業種やBtoB特有の商習慣に対応できるか
BtoB取引では、企業ごとに異なる「掛け率」の設定、承認フロー、締め日ごとの請求書発行など、複雑な商習慣が存在します。自社の業務フローを洗い出し、それに必要な機能が標準で備わっているか、あるいはカスタマイズで対応可能かを確認しましょう。
ポイント3:セキュリティ対策は万全か
企業間の取引情報を扱うため、セキュリティは最重要項目の一つです。不正アクセスを防ぐための通信の暗号化(SSL)、アクセス制限機能、データのバックアップ体制などがしっかりしているか、ベンダーのセキュリティポリシーを確認しましょう。
ポイント4:導入・運用時のサポート体制は手厚いか
特にIT専門の担当者がいない企業では、導入時の初期設定や運用開始後のトラブル時に、気軽に相談できるサポート体制があるかが非常に重要です。電話やメールでの問い合わせ対応はもちろん、導入支援の専門プランがあるかなどもチェックしておきましょう。
導入決定から運用開始までの4ステップ
システム導入は、計画的に進めることが成功の鍵です。
STEP1:課題整理と要件定義
まずは現状の業務フローを可視化し、「システムで解決したい課題は何か」「絶対に外せない機能は何か」を明確にします。
STEP2:情報収集と製品比較
要件定義をもとに、複数のシステムベンダーから資料を取り寄せ、機能や料金を比較検討します。無料トライアルがあれば積極的に活用し、操作性を確認しましょう。
STEP3:導入準備(データ整備・社内周知)
導入するシステムを決定したら、商品マスタや顧客マスタなどのデータを整備します。並行して、社内および主要な取引先にシステム導入の目的とスケジュールを説明し、協力を仰ぎます。
STEP4:運用開始と効果測定
まずは一部の取引先からスモールスタートし、徐々に対象を拡大していくのがスムーズです。運用開始後は、当初の目的(作業時間の削減など)が達成できているかを定期的に評価し、改善を続けます。
まとめ:受発注システムの導入は、企業成長の第一歩
本記事では、電話やFAXといったアナログな受発注業務が抱える課題から、システム導入による具体的なメリット、そして自社に合ったシステムの選び方までを詳しく解説しました。
受発注システムの導入は、単なる業務効率化ツールではありません。人為的ミスをなくして顧客満足度を高め、蓄積されたデータを経営に活かすことで、企業の競争力を根本から強化する戦略的な一手です。日々の煩雑な作業から解放されることで、従業員はより付加価値の高い創造的な仕事に時間を使えるようになります。
そして、特に製造業においては、スムーズな受注はゴールではなく、最適な生産体制を築くためのスタートラインに過ぎません。受注した情報を、いかに迅速かつ正確に「生産計画」や「部品発注」、「工程管理」に連携させるかが、納期遵守と品質維持の鍵を握ります。
もし貴社が製造業であり、「受注から生産、出荷までを一気通貫で管理し、会社全体の最適化を図りたい」とお考えなら、クラウド型生産管理システム「鉄人くん」がおすすめです。「鉄人くん」は、小規模な製造業の現場に特化し、受注管理はもちろん、生産計画、工程管理、在庫管理、原価管理までをシンプルに一元管理できるシステムです。
受発注業務の効率化をきっかけに、その先の生産プロセスまでを見据えたDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、企業のさらなる成長を実現しましょう。
また、トライアルキャンペーンも実施していますので、生産管理システムの導入を検討してみたいとお考えの方は、こちらからお気軽にお問合せ・ご相談ください。