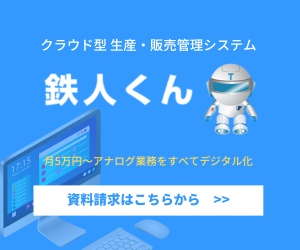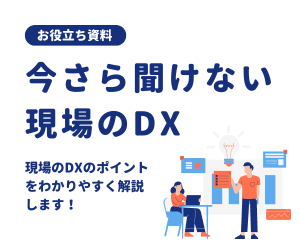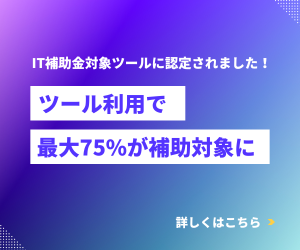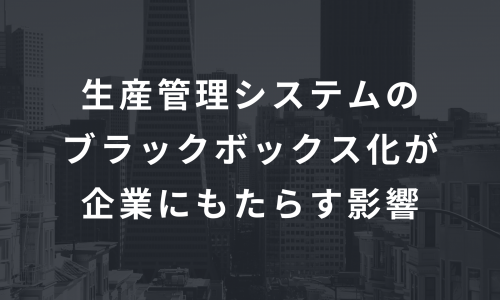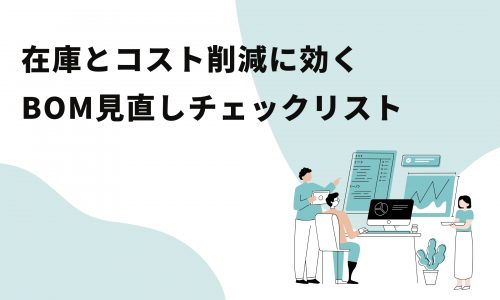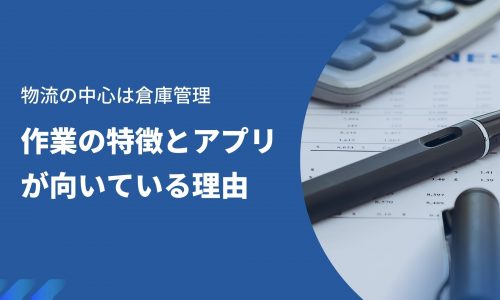2019年に経済産業省が公開した『DXレポート』では、ブラックボックス化したレガシーシステムが残存した場合、2025年までに最大12兆円/年の経済損失が発生する可能性があると指摘されました。また、そのことを『2025年の崖』と呼ばれています。当時は「2025年までまだ余裕がある」と考える企業も多かったかもしれませんが、まさに「2025年の崖」という表現が、いま再び現実味を帯びてきています。
出典:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」
ユーザ企業は、DXを実現できずデジタル競争の敗者となり、多くの技術的負債を抱え、業務基盤そのものの維持・継承が難しくなるでしょう。また、ベンダー企業は既存システムの運用・保守にリソースを割かざるを得ず、成長領域であるクラウドのサービス開発ができません。レガシーシステムサポートを継続するしかなく、多重下請構造から脱却できないのです。
3分でわかる!はじめてのDX
今さら聞けない現場のDXのポイントを解説!
お役立ち資料はこちらから無料ダウンロードいただけます。
1-1. 「2025年の崖」とは何だったか
「2025年の崖」とは、国全体でDXが進まずレガシーシステムを放置してきた場合に生じる膨大な経済損失を指す言葉です。既存システムが老朽化・複雑化し、メンテナンス要員も不足することで、次のようなリスクが高まると予想されています。
- システムトラブル増加: 障害時の修復が難しくなり、業務停止やデータ滅失が発生
- IT予算の大半が保守運用に充当: 新規開発やDX推進のためのリソース不足が深刻化
- デジタル競争での大きな出遅れ: 旧来システムに縛られ、新しいビジネスモデルやサービス構築が難しくなる
- ブラックボックス化の拡大: 担当者の退職などでノウハウが失われ、誰も手が付けられない状況に
当時の報告によれば、これらの問題を放置すると2025年以降、年12兆円の損失が国全体として発生しかねないとされました。それから年月が経過し、今、まさにこの懸念が一部の業界や企業で顕在化しているのです。
1-2. DXが注目される中での再燃
ここ数年、国を挙げて「DX推進」が叫ばれ、企業も先進技術を導入しようという機運が高まっています。ところが、実際には多くの企業がレガシーシステムに縛られて思うように移行できず、DXの恩恵を享受できていないケースが目立ちます。古い技術や仕組みをメンテナンスしながら、一部だけクラウド化やAI活用に手を出しても、全体最適からほど遠い状況に陥るのです。
自社独自のカスタマイズを重ねてきたシステムほど、ベンダー依存や属人的ノウハウに支えられています。これがDX推進時の最大の障壁であり、IT人材不足や技術継承の困難に拍車をかけています。加えて、新型コロナの影響でリモートワークが一気に進んだ結果、オンプレミスのレガシーシステムにアクセスできず業務が滞る現実も浮上し、問題がさらにクローズアップされました。
1-3. 今、どうするべきか
現在、下記のような緊急性が高まっています。
- システムの全社的棚卸し: どの部署がどんなレガシーシステムを使い、どれほど複雑化しているかを可視化
- 優先度をつけた刷新計画: 事業へのインパクトが大きい部分からクラウド移行やスクラップ&ビルドを検討
- DX人材の確保・育成: システムを丸投げにせず、内製化や人材育成で自社のデジタル基盤を強化
- 経営層のコミット: レガシーシステムの刷新にはコストも時間もかかるため、トップダウンの推進力が重要
「2025年の崖」はもはや“遠い将来のリスク”ではなく、“現在進行形の課題”として捉えなければなりません。これから取り組めばまだギリギリ間に合うかもしれませんが、先延ばしを続けるほど、対応が困難になっていくのは間違いありません。
1-4. 記事の構成と目的
本記事では、まず「レガシーシステム」とは何かを正確に押さえ、その問題点と「2025年の崖」が意味するリスクを再整理します。そして、どうすればレガシーシステムから脱却し、DX時代に適応できるかを具体的なソリューション例や取り組みのヒントを交えて解説します。製造業の経営者・現場責任者・DXやIT担当者が直面する課題を踏まえ、現実的な選択肢を提示することで、少しでも早い段階でのアクションにつなげていただければ幸いです。
レガシーシステムとは?
「レガシーシステム」は、新しい技術や環境に対応できず、古くなった技術的負債を抱えたITシステムを指す概念です。ただし、単に「古い=レガシー」というわけではなく、運用や保守が困難で、DXを阻害していることが主要な判断基準となります。ここでは、レガシーシステムの主な特徴や、その背景にある原因と問題点を掘り下げてみましょう。
2-1. レガシーシステムの一般的な特徴
- メインフレームやオフコンなど大型コンピュータを使用
主に1990年代以前に開発された基幹システムなどは、メインフレーム上で動作しているケースが多く、最新の技術やクラウドとの連携が困難。 - 構築から20年以上経過する長寿命システム
その間に担当者が何度も交代し、結果としてブラックボックス化している。文書化不十分でプログラムの全容を誰も把握できない状態に。 - 独自カスタマイズの塊
ベンダー依存や個人技術者のノウハウにより、「その人しか分からない」ロジックが組み込まれ、メンテナンス費が高騰。 - データ連携が困難
APIや標準プロトコルがなく、外部システムや新技術との統合が難しい。データの二重入力や手動管理が発生。
こうしたシステムは一旦稼働し始めると、止めることが大きなリスクになるため“技術的負債”を抱え込んだまま継続運用されがち。結果的に、年々保守コストが増大し、新しい機能やサービス開発にリソースを回す余裕が失われるのです。
2-2. レガシーシステムが抱える主な問題点
1. 維持管理コストの増大
年々古くなる技術に対応できるエンジニアが減少し、ベンダーもサポートを終了しがちです。結果として人材コストや特別な保守契約費が高騰し、IT予算の9割以上が運用維持に消えている企業も珍しくありません。「攻めのIT投資」ができないまま取り残されるわけです。
2. ブラックボックス化
構築から数十年が経過したシステムは、ドキュメントが散逸・消失している可能性があります。担当者の退職や外部委託先の廃業などにより、本来把握しているはずの仕様が不明瞭になり、何か変更を加えようとすると大きなリスクが伴います。メンテナンスや小さな改修すら、莫大な工数や費用がかかる事態に。
3. セキュリティリスク
古いOSや開発言語を使っている場合、ベンダーのサポート切れでセキュリティパッチが提供されないケースがあります。外部と接続が増えるDX時代には、こうした穴がサイバー攻撃や情報漏洩の原因となり得ます。表面上は動いているように見えても、根本的に安全性が脆弱化している可能性が高いのです.
4. DX実現の足かせ
IoTやAI、クラウドを活用しようにも、レガシーシステムがデータ連携のボトルネックとなり、現場でのリアルタイム可視化や分析が困難になります。結果的に他社がDXで成果を上げている中、旧来の作業フローを変えられず競争力が低下するリスクが避けられません。
2-3. なぜレガシー化してしまうのか:原因分析
- 担当者の退職・ノウハウ流出
古いシステムを知り尽くしていたベテランが辞め、若手は新技術に興味を持つため触れようとせず、結果としてブラックボックス化が進行。 - 繰り返される部分最適
部門ごとに別々にシステムを拡張してきた結果、全体の整合性が崩れて統合が難しい。 - 外注頼みの開発
中小企業では特に、すべてベンダー任せにしてきたため、システム構成やコードを社内で管理できず、ベンダーロックインが発生。
こうした経緯から「仕方なく使い続ける」状態が長引き、新しいサービスやアプリケーションとの連携が著しく困難になるのが現状です。
2-4. 今後の展望:レガシーシステムへの対応急務
製造業では、これまで堅牢に動いていたメインフレームが急に使えなくなるわけではありません。しかし技術者の世代交代や規模拡大、海外展開などを踏まえると、いつまでもレガシーに依存していると競争力を維持できなくなる可能性が高いです。逆に、今の段階で積極的にレガシーシステムの見直し(マイグレーション・モダナイゼーション)に着手した企業は、DXを武器に国内外の市場で優位に立つことが期待できます。
レガシーシステムから脱却するための手段:モダナイゼーション・マイグレーション・クラウド活用
レガシーシステムの刷新は一筋縄ではいきません。特に、製造業は基幹業務や生産ラインを止めるリスクが大きいため、大掛かりなシステム更改に踏み切れないジレンマがあります。しかし、放置すれば「2025年の崖」が現実化しかねない中、何らかの手を打たなければいけません。ここでは、主要な対策であるモダナイゼーション、マイグレーション、クラウド活用の3つを紹介します。
3-1. モダナイゼーション:現行システムを現代技術でリニューアル
モダナイゼーションとは、既存のシステム資産(ソフトウェアやデータ)を活かしつつ、最新技術を導入して再構築する手法を指します。具体例としては、メインフレームのアプリケーションロジックをJavaなど新しい言語に置き換えたり、UIをWebベースに変換したりするケースがあります。
- メリット:
- 現行システムの実績やノウハウ、データをある程度活かせる
- 新規開発に比べて期間やコストが抑えられることが多い
- デメリット:
- 古い構造を部分的に残すため、完全リプレイスより性能・拡張性で制限が残る場合も
- 移行プロセスが複雑化し、想定外の不具合が出るリスクがある
製造業でモダナイゼーションを採用する場合、工程管理や在庫管理など現場のプロセスを大きく変えずにUIやプログラムを刷新できる点が魅力です。しかし、適用範囲や優先度を慎重に見極めないと、「結局大半を作り直し」という事態にもなり得るので注意が必要です。
3-2. マイグレーション:新環境への移行でレガシー脱却
マイグレーションは、レガシーシステムから完全に抜け出すため、新しいプラットフォームやソフトウェアへ移行する選択肢です。オンプレミスのメインフレームやオフコンから、クラウド環境や標準化されたERPシステムなどに移すことが典型的な例として挙げられます。
- メリット:
- 根本的な刷新により、古い技術に依存しない柔軟な開発・運用が可能
- クラウドや新世代のソリューションと連携しやすく、DX推進に有利
- デメリット:
- 一度に大規模な切り替えを行うため、初期投資が大きくプロジェクトリスクも高い
- 現行システムを全停止するタイミングが必要になり、業務への影響が避けられない
製造業では、24時間稼働のラインや多拠点のサプライチェーンを持つ企業も多く、一気にマイグレーションを実施するのは極めて難しいです。そのため、段階的にサブシステムからクラウドに移行していく方法をとる企業が増えています。
3-3. クラウドサービス(SaaSなど)の積極利用
レガシーシステムから脱却するもうひとつの手段が、SaaS型クラウドサービスを導入することです。具体的には、ERPや生産管理、在庫管理などをクラウド対応のパッケージに置き換える形が挙げられます。
メリット
- 導入が手軽: インストールやサーバー保守が不要で、アカウントを用意すればすぐに開始可能
- 低コストで運用: 初期投資を抑え、月額・年額などのサブスクリプションモデルで利用できる
- 自動アップデート: ベンダー側がソフトウェアを最新版に保ってくれるため、セキュリティや機能面の更新が手間にならない
デメリット
- カスタマイズ性の制限: SaaS型は標準機能での運用が基本で、大幅な業務変更が困難な場合も
- 外部依存リスク: サービス提供元の都合で機能や料金が変わる可能性がある
- ネットワーク前提: インターネット障害時にアクセスできない懸念がある
製造業のDX推進を考慮すると、クラウドファーストを原則とする企業が増えています。部分的には現行システムを残しつつ、クラウドで新たな領域(例えばIoTデータ収集やBIレポートなど)を運用し、徐々に移行を拡大していくハイブリッドアプローチも多く見られます。
3-4. メリット・デメリットを踏まえたアクションプラン
レガシーシステムからの脱却は、単なる技術置換にとどまらず、企業の業務フローや人材育成、パートナー関係などさまざまな要素と連動する大規模プロジェクトになります。以下のステップがおすすめです。
- ロードマップ策定: 現行システムをどこまで何年で置き換え、何をクラウド化するのかスケジュール化
- 段階的実装: すべてを一気に変えるのではなく、部門や機能を区切ってリスクを小さくしながら進める
- 並行運用と検証: 新旧システムを一時的に併用し、不具合や問題を早期に抽出し是正
- 人材育成とチーム強化: 内製化をめざしたデジタル人材の確保、外部パートナーとの協力体制確立
- モニタリングと改善サイクル: DX施策やシステム刷新の効果を定期的に測定し、追加投資の判断材料に
こうした綿密な計画と実行体制を整えることで、「2025年の崖」というリスクを回避し、新たな価値創出につなげることが可能になります。
まとめ
レガシーシステムは、単に古い技術を使っているだけではなく、企業がDXを実現するうえで大きな足かせとなり得る存在です。特に今、リスクが高まっており、システム老朽化と人材不足の両面から経営や競争力に重大な影響を与えかねません。
そのため、レガシーシステムの刷新や移行は単なるITプロジェクトではなく、経営課題や現場オペレーションの改革として捉える必要があります。モダナイゼーションやマイグレーション、SaaSなど複数の選択肢を比較検討し、部分的に段階を踏みながらクラウドサービスを活用するのが現実的かつ効果的なアプローチです。
こうした取り組みをよりスムーズに進めるためには、在庫管理や生産管理、さらには購買や販売情報といったデータを一元管理できる仕組みが不可欠です。ここでおすすめしたいのがクラウド型生産管理システム「鉄人くん」の導入です。クラウド型で操作しやすい「鉄人くん」は、レガシーシステムに代わる新たな基盤としても、既存システムと連携しながら段階的にDXを推進するサポートとしても、大きな力を発揮します。ぜひ「鉄人くん」を活用して、レガシーシステム問題を解消し、2025年の崖を乗り越えていきましょう。
3分でわかる!はじめてのDX
今さら聞けない現場のDXのポイントを解説!
お役立ち資料はこちらから無料ダウンロードいただけます。
クラウド型生産管理システム「鉄人くん」は、わかりやすい画面と手厚いサポートで、システムが初めても企業でも使いやすくわかりやすいのが特徴です。
また、トライアルキャンペーンも実施していますので、生産管理システムの導入を検討してみたいとお考えの方は、こちらからお気軽にお問合せ・ご相談ください。

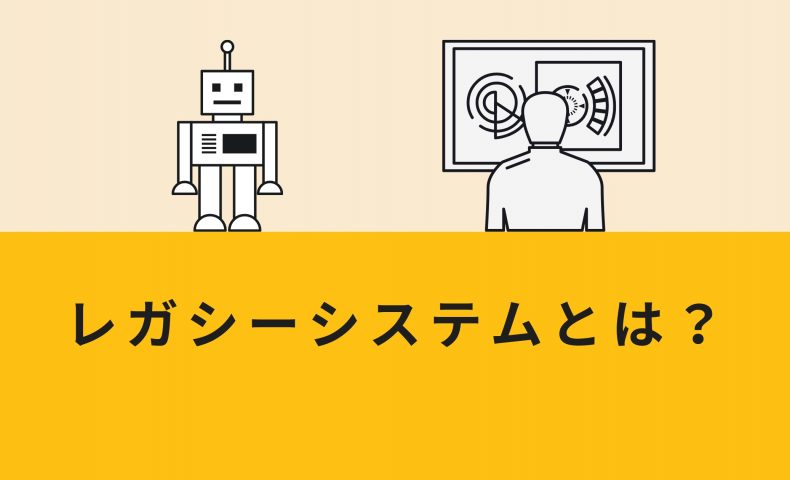
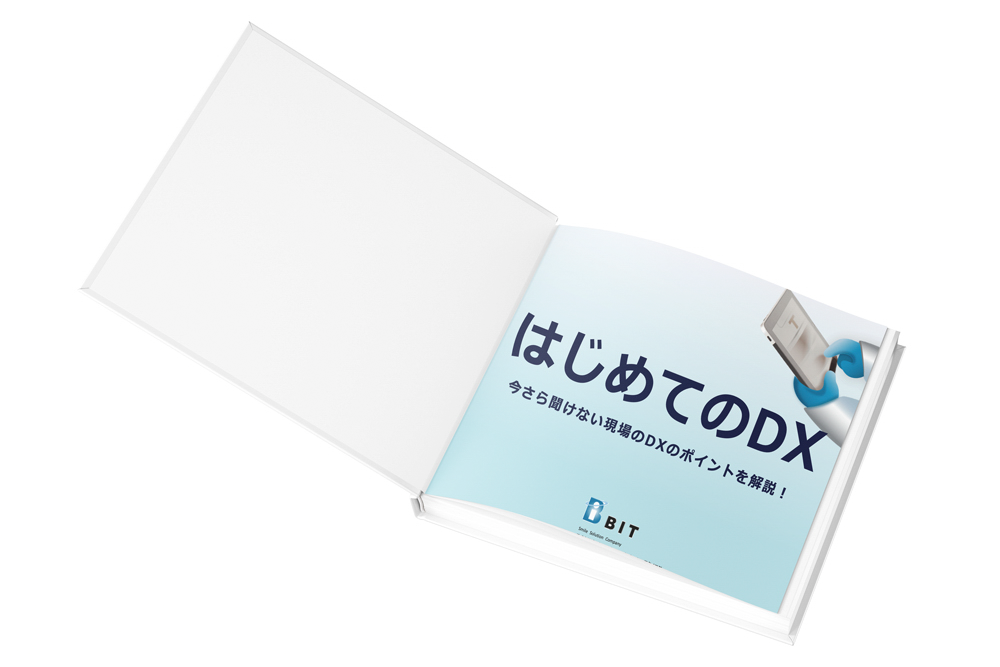
のすべて-200x200.jpg)